8月13日に紀尾井町オフィスにて、生成AI利活用事例に関するLT会「Hacking Fest 2025 Summer」を開催しました。
当日はオフライン・オンライン合わせて多くの方にご参加いただき、2025年上半期に取り組んだ�技術キャッチアップや個人開発の成果に関して、活発な意見交換や質疑応答が行われました。

開催の経緯
このイベントは2025年春に行ったGW中に行った技術キャッチアップや個人開発を発表するLT会の第2弾です。
今回は「生成AI利活用」にフォーカスし、技術的な知見や開発成果、実際の活用事例など幅広いテーマで発表が行われました。
前回と比べて、より多くの部署からの参加者があり、生成AIに関する技術的な知見や開発成果を共有する場を用意することで、2025年上半期の取り組みを振り返る良い機会となりました。
発表内容ダイジェスト
1. よく使われる生成AIモデルの能力比較
発表者:Yamada Kentarou
GPT、Claude、Geminiなど複数の生成AIモデルを対象に、リポジトリ要約・コード生成・特徴分析といったタスクで能力を比較した実験結果を発表していただきました。
各モデルの癖や得意分野、実際の出力例を交えながら、どのタスクにどのモデルが適しているかを丁寧に解説。特に、GPTは万能型、Claudeは分析や説明が丁寧、Geminiは効率的なコード生成が得意といった違いを分かりやすくまとめていただき、タスクごとにモデルを使い分ける指針となる内容でした。
2. AIエージェント開発で得た学び
発表者:Suzuki Kosuke
業務支援AIエージェントの開発を通じて得た知見を紹介していただきました。
プロンプトの微細な変更が出力全体に大きく影響するため、継続的な評価やプロンプト設計の分離が重要であること、LLMにしか任せられない作業のみ任せ、予想外の出力変化を防ぐ設計の工夫など、実践的なTipsを多数共有していただきました。
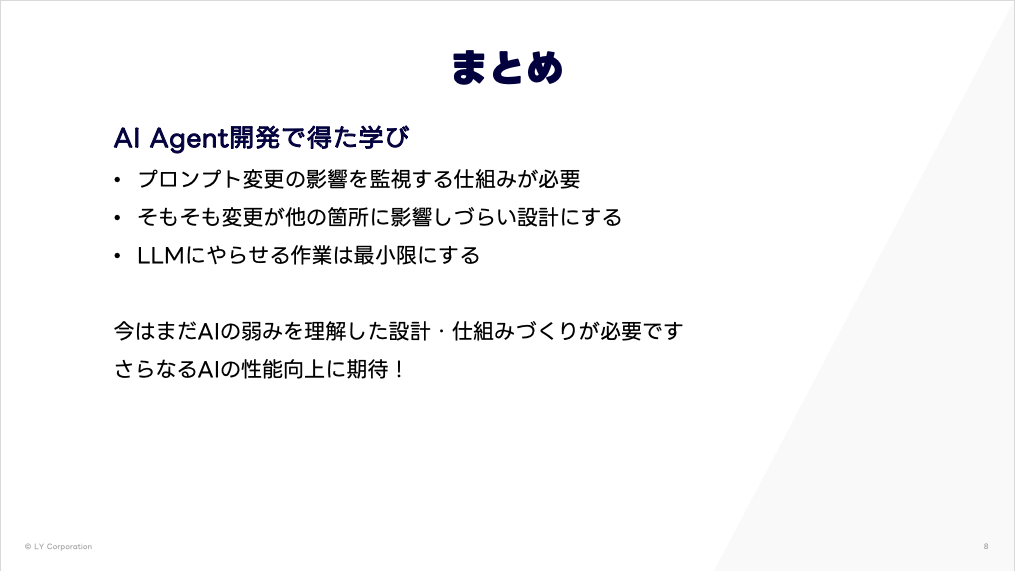
3. MCPの管理をProxyサーバーで楽にする
発表者:Suzuyama Hidehisa
社内外で増え続けるMCPサーバーや生成AIツールの設定・権限管理の煩雑さを解消するため、Proxyサーバーを自作した事例を発表していただきました。
複数のMCPサーバーを一元管理し、認証やツールの動的制御、ログ分析も容易になり、設定の手間や権限管理の課題を解決し、非エンジニアでも扱いやすいダッシュボードを実現。プロキシ依存や仕様追従の難しさなど、実装して分かった課題等も共有していただきました。
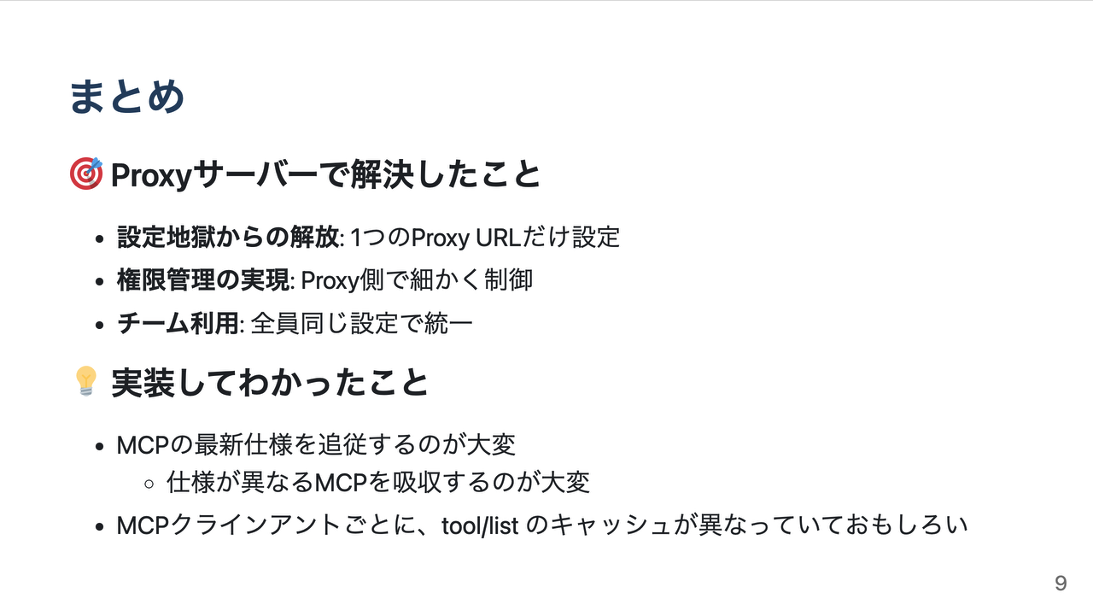
4. 雑に振り返る生成AIの発展過程
発表者:Kwon Soonhwan
生成AIの進化を、事前学習型言語モデルの登場からRAG・エージェント・マルチエージェントの最新トレンドまで、技術�的な流れを分かりやすく解説していただきました。
ベクトル検索やエージェントのオーケストレーションなど、現場での活用イメージや今後の展望も交え、生成AIの全体像を俯瞰できる内容でした。
5. AI Deep Researchガチンコ対決 〜2025お盆帰省スペシャル〜
発表者:Keishima Amon
「AI Deep Researchガチンコ対決」と題し、実家への帰省ルート選定をAI各モデル (Gemini 2.5 Pro Deep Research, Claude Opus 4.1 Research, GPT-5 Thinking Deep Research) に任せてみて、結果を比較するというユニークな実験を発表していただきました。
各モデルの提案ルートの精度を比較し、実際のやりとりやアウトプットの違いを楽しく紹介。最も納得感のある結果を出したモデルがあった一方で、意図と異なる提案で失格となったモデルもあり、AIの実用性と “人間らしさ” の違いが浮き彫りになった内容でした。
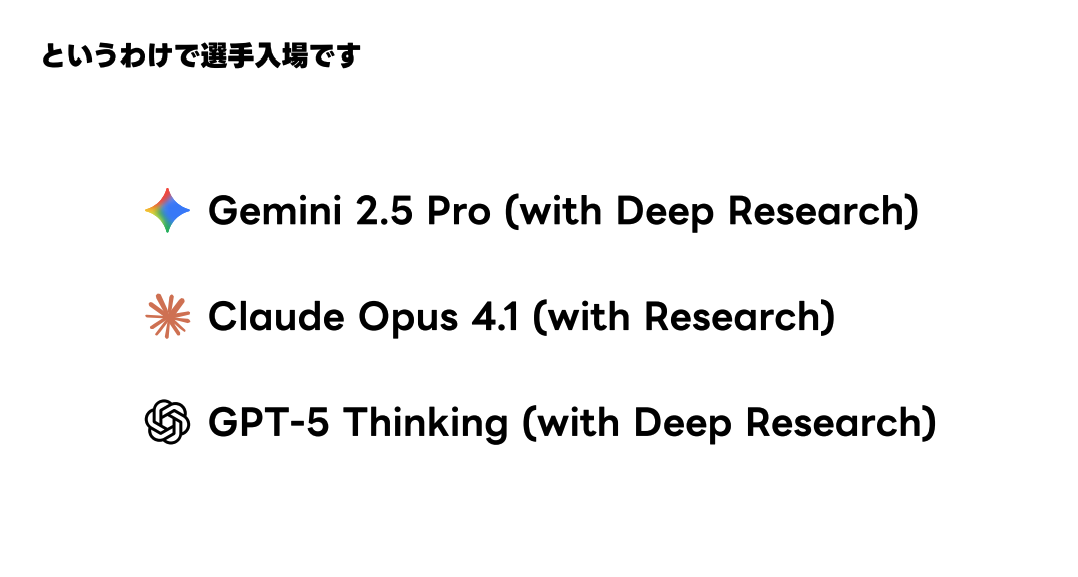
6. Claude Code Actionの導入と活用例
発表者:Itai Toshiki
チームでClaude Code Action (GitHub Actions上でClaudeを活用する仕組み) を導入し、コードレビューやPR作成、細かな修正の自動化など、実際の活用例を紹介していただきました。
プロンプトと結果がPR上で議論できるメリットや、レビュールールの進化、スマホからの簡単な修正依頼など、現場での具体的な使い方と可能性を�共有していただき、チーム開発におけるAIエージェント活用の広がりを感じさせる内容でした。
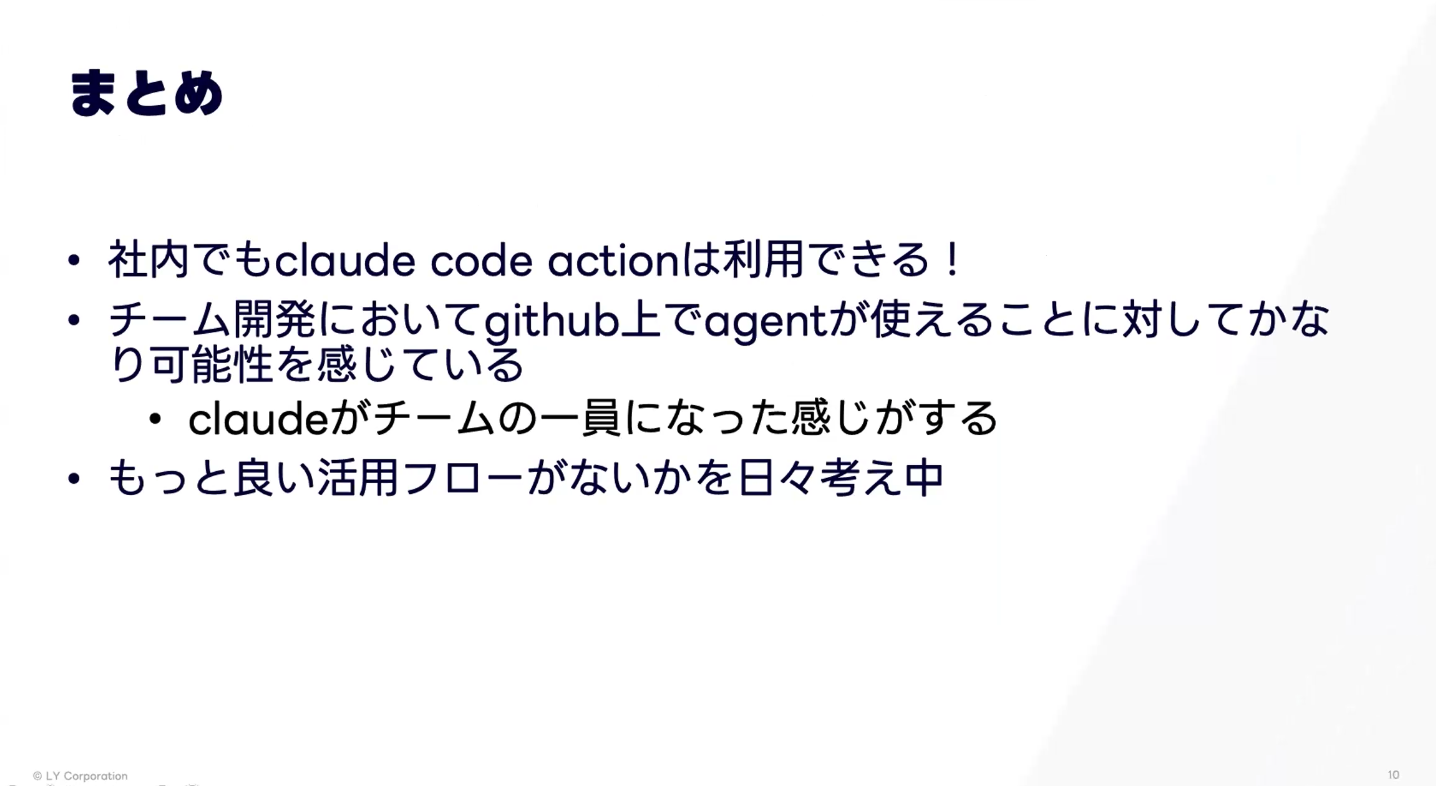
7. AIで個人開発を加速させたら14,000円浮いた話
発表者:Hanatani Takuma
個人開発でAIを活用し、今まで契約していたサブスクを解約して約14,000円のコスト削減に成功した体験談を発表していただきました。
あえて現行のベストプラクティスから外して「大きな仕様をAIに丸投げ」し、短時間で実用的なツールを自作したプロセスや、業務でも活用できるレベルの精度を実現した工夫を紹介していただき、AI活用による時短・コスト削減のリアルな事例として、参加者の関心を集めました。
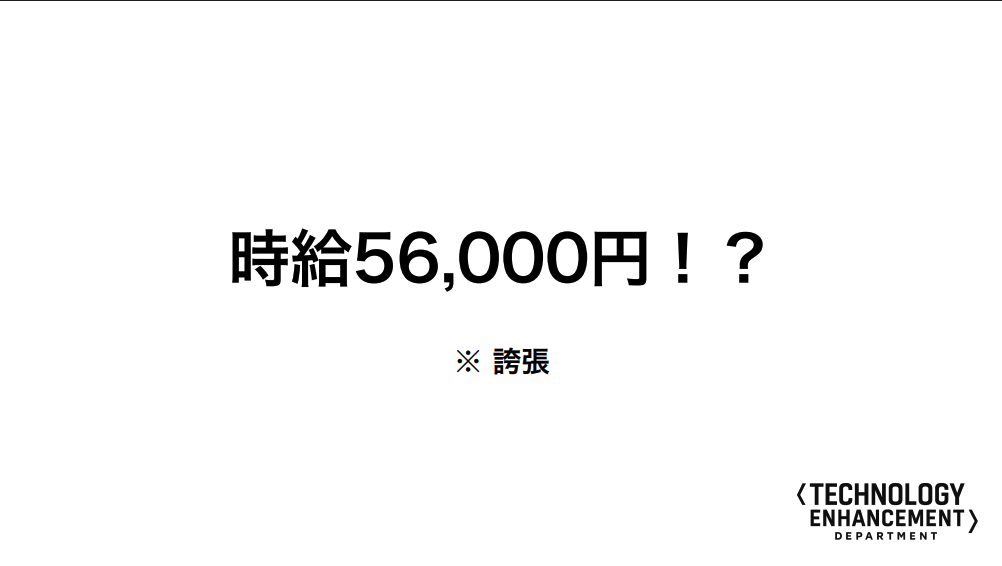
8. Confluenceの操作をMCP化して楽ちんにする
発表者:Maekawa Kohei
Confluenceの検索やページ作成、翻訳などの操作をCLIツールとMCPサーバーを組み合わせて自動化した事例を紹介していただきました。
API仕様や認証の煩雑さ、LLMによる自動化の難しさをCLIで抽象化し、エラー処理やプロンプト設計の工夫で実用的な自動化を実現。実際の利用例や課題、今後の展望も紹介していただき、社�内外での業務効率化のヒントとなる内容でした。
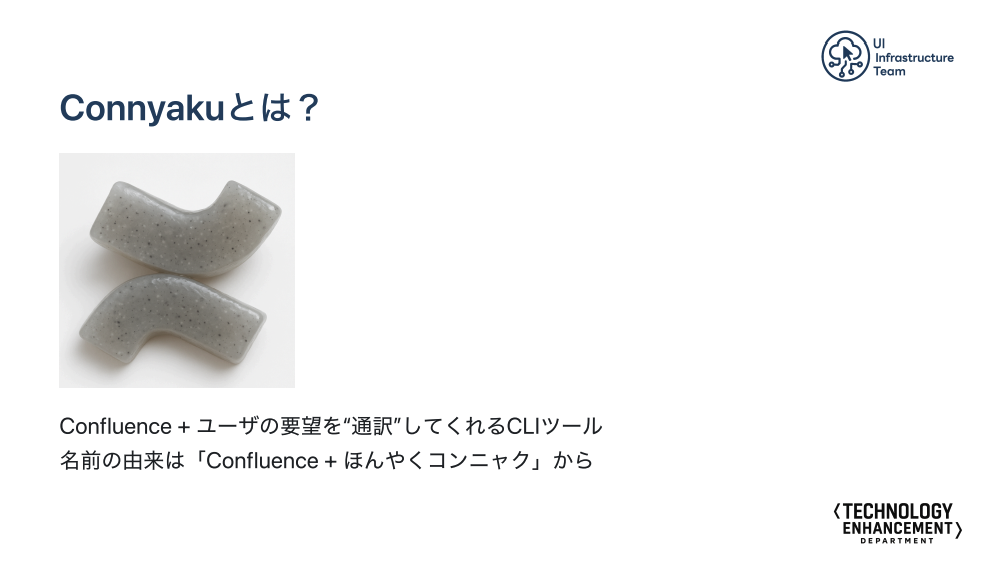
9. Belcheroを社内プラットフォーム情報MCPを使って導入する
発表者:Sueishi Hiroki
社内のNode.jsホスティングサービスを、社内プラットフォーム情報MCPを活用してどこまで簡単に導入できるかを実験した事例を発表していただきました。
MCP経由でプロンプトを入力するだけで、Node.jsサービスのセットアップや設定ファイルの自動生成が可能に。実際の導入プロセスや、サンプルリポジトリの配置・設定の工夫、生成AIの挙動に合わせた手直しポイントなど、現場で得た知見を具体的に共有していただき、MCP活用の可能性と課題をリアルに伝える内容でした。
まとめ
今回のLT会は、部署やチームの垣根を越えて、生成AIの最新動向や実践的な活用事例、現場での工夫など、多くの知見や学びを共有できる貴重な機会となりました。参加者同士の交流も活発で、今後の業務や個人開発に活かせるヒントも多数得られ、当初の目的であった技術交流と成長の場として大きな役割を果たせたと感じています。
多くのメンバーに参加してもらえた割に発表のハードルを低く抑えられたことも好評でした。
今後もこのようなイベントを定期的に開催し、さらなる技術交流と成長を目指していきたいと思います。次回の開催もぜひご期待ください!


