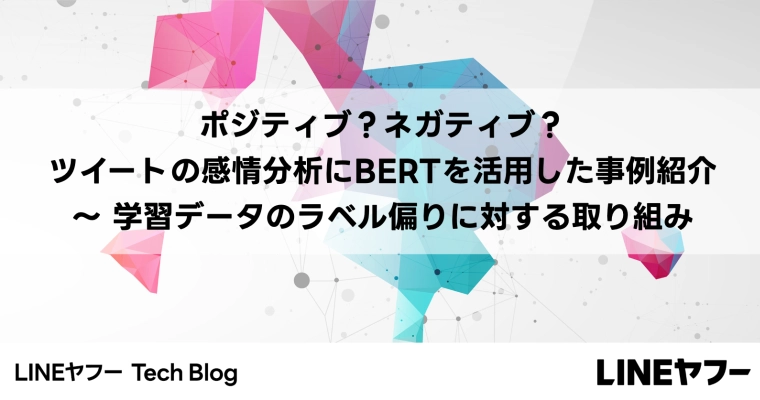こんにちは、Go言語サポートのリードを担当している櫻山です。
2025年9月に開催された「Go Conference 2025」にLINEヤフーとして初めてスポンサー協賛し、社内のエンジニア3名で参加しました。本記事はそ�のレポートです。
1. 初参加のきっかけ
今回、LINEヤフーとして初めてGo Conferenceに参加しました。コミュニティ参加を始めるヒントになればと思い、その経緯について説明します。
LINEヤフーにはGo言語の利用をサポートするチームが存在します。本チームは、主に社内環境の整備(ツールやライブラリの提供など)と、社内Goユーザーからの問い合わせ対応を担当しています。また、複数の部署からの兼務で構成されているため、Goに関するプラクティスや技術動向を共有するネットワークを築いており、社内コミュニティの中心的なメンバーでもあります。
当チームは前期から「コード・知識・エンジニアの好循環」をビジョンに、既存の役割に加え「イネーブリングチーム」としての役割を再定義しています。単にツールや知識を提供するだけではなく、ユーザーの自律的な成長を支援することを目的として、社内コミュニティのあり方を模索しています。
その取り組みの一環として、社内からチーム横断で希望者を募り、Goの国内最大級カンファレンスであるGo Conferenceに参加することにしました。同時に、ブロンズスポンサーとして協賛しました。
それでは、Go Conference当日の様子とそこから得られた学びについて書いていきます。
2. Go Conference 2025 当日の様子
カンファレンスは9月27日・28日の2日間にわたり開催されました。

フロアは二つに分かれ、一つはセッションとワークショップが行われ、もう一つはスポンサーブースが設営されました。それぞれ説明します。
セッション
セッションは両日ともにほぼ1トラックで実施されました。聴講者は部屋移動を抑え、セッションに集中することができました。セッション後はスピーカーQ&Aが設けられ、有識者から直接質問して深掘りすることができました。
以下は参加者によるピックアップです。
「encoding/json/v2で何が変わる? - v1からv2への変化を徹底比較」/ glassmonkeyさん
標準パッケージのencoding/jsonをトピックとしたセッションです。まずv1での課題を指摘した上で、v2では内部設計が構文と意味の2層に分離されたことによってもたらされた改善が次のように紹介されました。
- 柔軟性: 2層構造によりio.Reader/io.Writerが利用可能になり、基本的な使い勝手を保ちながら拡張性が向上。
- 正確性: RFC8259に準拠し、不正なJSONを厳密に検出。エラー位置も正確に報告されるようになった。
- 効率性: ストリーミング対応によりメモリ効率が向上し、トークン単位での処理や並列化も可能になった。
- 互換性: v1互換モードを備え、既存コードを安全に移行できるようになっている。
「Go で WebAssembly を利用した 実用的なプラグインシステムの構築方法」/ goccyさん
プラグイン機構の現状と��、WebAssembly (WASM)を用いた新しいアプローチが紹介されました。
従来のプラグイン機構には、Goモジュールのバージョン互換性、CPUアーキテクチャ差異、クラッシュの伝播といった課題があると指摘されました。
一方、WASMを利用すると、サンドボックス環境で安全かつ移植性の高いプラグイン実行が可能になります。ただし、WASI Preview 1はネットワークソケットやスレッドに未対応であるため、並行処理、メモリ管理、ネットワーク、TLS、外部コマンド実行といった点に課題が残ります。
発表では、こうした制約を標準ライブラリの差し替えやホスト側への処理委譲によって克服する実践的な手法が説明されていました。
「Go1.25から正式リリースされたsynctestとdurably blockingについて」/ Panaさん
標準パッケージとなったtesting/synctestが紹介されました。この新機能は、実行に時間と不安定さを伴いがちな並行テストをサポートします。発表では、簡単な導入によってテストの実行時間を大幅に短縮できた具体的な事例が示されました。
「panicと向き合うGo開発 - nilawayで探る見逃されるnil参照とその対策」/ Shoki Hataさん
nil参照を事前に検知するツールが紹介されました。多くを検知できる一方で、偽陽性などの制限に触れており、静的解析ツールとの向き合い方の参考になりました。
各発表は記事の最後にリンクしています。
ワークショップ
ワークショップは予約抽選制で、初日の��み開催されました。
今回の参加者は残念ながら誰も参加できなかったのですが、当日偶然会った知り合いの社員から以下の感想が聞けました。
- 使ったことのないライブラリやツールを簡単に試せた
- 他社の方と交流しながら課題を楽しめた
- 参加できなかったワークショップも、アップロードされた資料が参照できてよかった
特に、ymotongpooさんによる「今日から始めるpprof」は、Goの代表的なプロファイリングツールであるpprofを演習形式で体験できるものでした。この資料は社内でも活用できそうだと感じました。
初学者が楽しめるトピックも多く、部屋の外から見ても誰でも楽しめる雰囲気がありました。大きなカンファレンスでありながら、参加者同士の交流が活発なGo Conferenceの良さが表れていました。
スポンサーブース
スポンサーブースは一つ上のフロアに設営されました。セッション・ワークショップのフロアと分かれていたにもかかわらず両日ともににぎわっていました。
以下が全体的な感想です。
- ブースの担当者はフレンドリーな方が多く、技術や業界の話題で交流できた
- 特にGoならではのパフォーマンスチューニングについてエンジニア同士で共有できた
- いくつかのブースに設置されたアンケートボードは、Gopherの声が直接反映されており技術動向や課題感の参考になった
- スタンプラリーと景品が用意されており、ブース巡りの動機づけが工夫されていた


どのブースも凝っていましたが、特に株式会社ナレッジワークのブースがおもしろかったです。パネルに出題されたコードに付箋でレビューしていくというもので、Goの書き方や他の人の視点が学べました。単に是非を判断するクイズと異なり、イネーブルメントを目的にみんなでコメントするというフォーマットが学習コンテンツとしても優れていると思いました。時間ごとに出題も変わり、何度も足を運びたくなるブースでした。
3. 初参加で得た気づき
全体として多くの気づきがありました。
- イベント全体的に分け隔てなく楽しめる工夫や雰囲気があり、新しい交流を生む機会が多かった
- 社外のエンジニアとの交流を通じて、Goユーザーに共通する課題や解決策を共有できた
- 社内のエンジニアがGoの最新動向やプラクティスを学べた
- 後日社内で感想戦を行うことで、個人で参加するより多くの学びを共有できた
- 上記のように、社外コミュニティへの参加が社内コミュニティのイネーブルメントを高める一手段となることを確認できた
また、今回のカンファレンス参加と協賛は社内のDevRelの協力により実現できました。まだコミュニティ参加に踏み込めていない方は、カンファレンスを知る方に気軽に聞いてみると、思った以上の協力が得られるかもしれません。
4. まとめ
LINEヤフーとして初めて参加・協賛したGo Conference 2025は、組織横断の交流を深め、社外の最新技術動向や課題感を共有する大変実りのある機会となりました。今回の参加を通じて、コミュニティへの参加が技術のイネーブルメントを高めるポテンシャルを実感しました。
最後に、本イベントにご協力くださった登壇者、運営スタッフ、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。
関連リンク
- セッション
- ワークショップ
- ブース
- 「Go Conference 2025 にシルバースポンサーとして協賛しました / 株式会社ナレッジワーク」Zenn
(同社の記事一覧をたどると出題ごとの解説記事が見つかります)
- 「Go Conference 2025 にシルバースポンサーとして協賛しました / 株式会社ナレッジワーク」Zenn